大学入試にも直結!
私学の『探究学習』に迫る
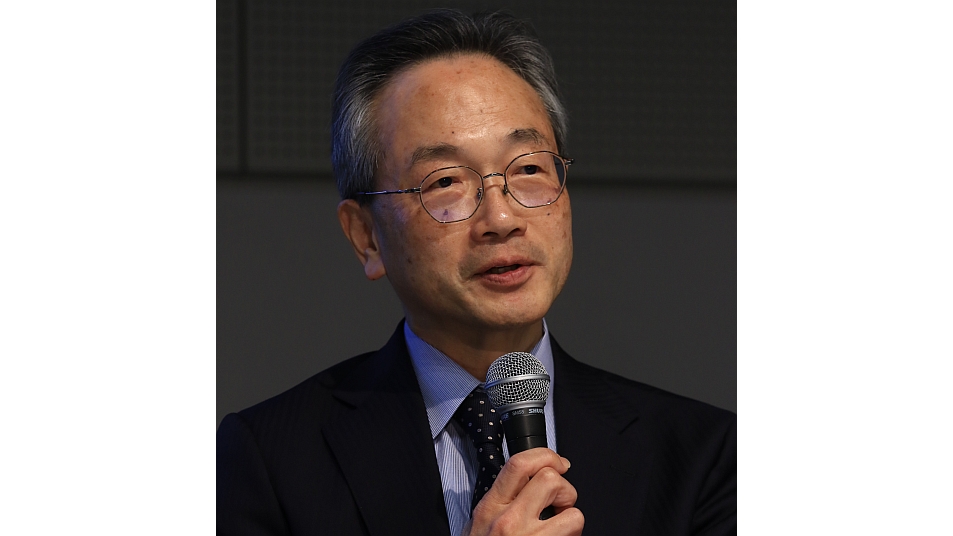
西大和学園中学校・高等学校 高等部高1学年部長
西村 広展先生
[2]企業・大学・自治体との連携も
広野 学校のなかにとどまらず、企業・大学・自治体など、外部と連携した探究活動も行われています。どんな活動がありますか。
西村 高校生になると、大学と連携した自由研究に取り組んでいます。最も大切なのはテーマ決めです。たとえば実際に行われた「カイコの記憶の保持」という研究では、最初に高校生から出てきた時は「カイコについて」という漠然としたテーマでしたし、「光合成細菌を用いた硫化水素の除去」というテーマも、最初は「光合成細菌について」で、どこに研究の本質があるのかわからない状態でスタートしました。こうしたテーマを深めていく時に、いろいろな研究者に協力を依頼しています。テーマ決めの際は、まず教員と卒業生TAでどういうところがおもしろいのかを一緒に議論します。中3まで課題研究をやってきた生徒たちは活動のレベルが高く、大学を調べていろいろな先生にアプローチするメールを出していきます。奈良先端科学技術大学院大学など、奈良にある大学には特に協力してもらっています。
光合成細菌に関しては、硫化水素の除去に使えるのではないかと、テーマに対するサジェスチョンをいただきましたし、テーマを決めた後も実験をしながらオンラインでアドバイスをもらうなど、高校にいながら大学の先生からアドバイスをもらう研究室のような環境を作ることができています。さらに中間発表でも大学の先生から意見をいただくなど、大学院生さながらの研究の状況を構築しつつあります。大学の先生を招いて話をしてもらうだけではなく、何よりも生徒たちがしっかりとした探究心を持った状態で大学の先生にアプローチすることによって、大学の先生も前向きに協力くれているところがあります。そのチャンネルも多ければ多い方がいいと思っています
立山 今年度より産官学推進委員会という部署が立ち上がり、その一端として、大阪産業局と包括連携協定を結びました。これは中高では日本初です。連携して女子中高生向けのキャリアプログラムを開発するなど、女子のロールモデルの構築をめざす活動を始めています。3月には中2・3年の生徒約40名が理化学研究所との連携で「AIと人がつながる未来図」をテーマに、一般企業の方などもお招きして研究発表会を行いました。世界的に女性の研究者は非常に少なく、特に日本人女性となれば更に希少な存在だそうで、その解消策としてロールモデルを作るためにこうしたイベントを実施しました。AI分野の第一線で活躍中の先生方に関わっていただき、そこで学んだことをもとにポスターを作り、プレゼンする企画です。先を歩く女性研究者の姿を見てほしいという思いもあり、協力をしてもらったのはすべて女性の先生です。先生方からは研究内容だけでなく、「結婚・出産となると日本の社会はまだまだ難しい、ただ研究者はすぐに現場に戻ることができるし、自分のしたいことを追求できる、こんな幸せなことはない」というお話を伺うこともできました。また、記事の作り方やインタビューの仕方は読売新聞社に協力いただくなど、まさに産官学の取り組みが実現できました。学内だけでは経験できないものだったので、非常に良かったと思います。
もう一つ、大阪公立大学とは共創パートナーシップを締結しました。これも中高では日本初の試みで、単にキャンパスを見学するだけでなく、新しくできた施設で中高生向けのアントレプレナーシップ教育を受けたり、小型宇宙機やクリーンバイオについて学んだりと、今後さまざまな企画を考えています。
神田 課題研究に取り組むにあたっては、アドバイザーとして大阪医科薬科大学生理学教室の先生に入ってもらっています。生徒がグループ単位で実験の計画を相談すると、先生から具体的なアドバイスをいただけます。実際に実験室でいろいろな実験をしているところです。また、同じく大阪医科薬科大学で魚の研究をしている先生に講演に来てもらったりもしています。それ以外にも基礎医学講座や基礎薬学講座など、高大連携講座を数々実施しています。生物部の部員がぜひこの先生から話を聞きたいとお願いをして、当時の魚類学会会長の先生に講演に来てもらったこともあります。生物部OBが講演に来てくれることもあり、大学の先生や卒業生と仲良く連携しながら探究活動に取り組んでいます。



